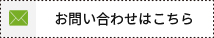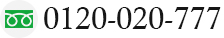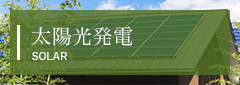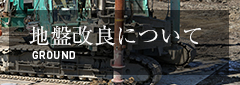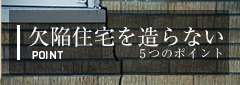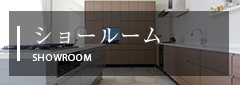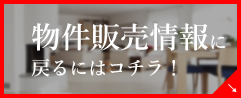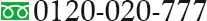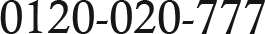地鎮祭とは

地鎮祭とは、土木工事を行う際や建物を建てる際に、工事の無事や安全と建物や家の繁栄を祈る儀式のことを言います。
「じちんさい」と読むほか「とこしづめのまつり」と読むこともあります。
「鎮」の字にはしずめる、落ち着かせるといった意味があります。
工事の着工にあたり、神職をお招きして神様にお供え物をして、祝詞をあげ、お祓いをして浄め、最初の鍬や鋤を入れ、工事の無事を祈ります。
上棟・上棟式とは

上棟とは、家を建てるとき、骨組みを組み立てて最上部に棟木(むねぎ)を上げること。また、上棟式とは、建物の守護神と匠の神を祀って、棟上げ(上棟)まで工事が終了したことに感謝し、無事、建物が完成することを祈願する儀式。
しかし、現在の上棟式では「儀式」というよりも施主様が職人さんをもてなす「お祝い」の意味が強くなっており、「地鎮祭」や「上棟式」を略式でされる方が多くなっています。
上棟式は地鎮祭と違って神主さんに来て頂くことがないため(地域によっても異なります。)現場監督が式を進めることがほとんどです。
地鎮祭や上棟式の費用は基本的に施主様負担ですので、必ずしも行わなければならないわけでは御座いません。
最近では、どちらも行わない方も珍しくは御座いません。